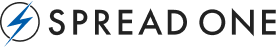デザインの最適化とサドルポイント
おそらくこのページを閲覧されている方からは、タイトルにあるサドルポイントという言葉は、耳慣れない言葉なのではないでしょうか?
サドルポイントは、ゲームの理論の重要な概念なのですが、ゲームの理論と聞いたら数学的にとても難解なものというイメージを持ってしまうかもしれません。でも、何かを最適化しなければならない問題に対処する際には、サドルポイントの考え方のエッセンスを少し知っていて、意識しているのといないのとでは、excellentなのかgoodなのか程度には、結果に差がでると考えています。
さてさて、デザインを最適化する際にも使えるサドルポイントとは、どのようなコンセプトなのかというと、考え方は至ってシンプルです。
例えば、あるWebページの一部の表示要素が少し大きすぎると感じられるので、少し小さくしてみようという場合を例にとって説明してみます。この場合、まずは、一回り小さくしてみます。その結果、見栄えが良くなったので、ここでOKとなる場合が多いのではないかと思います。
しかし、これが最適か?というと、最適とまでは言いきれない状態なのではないかと思います。そこで、もう一回り小さくしてみたところ更に良くなったとします。
ここでもOKを出さないのがサドルポイントを探っていくデザインの最適化方法です。ここで満足せずに更に小さくするのです。すると、何度かこの工程を繰り返すうちに、「小さくなり過ぎたかな!」と感じるタイミングが、いずれ訪れます。その直前が、最適化された「サドルポイント」になるという考え方です。人によって感じ方のバイアスもあるので、数名に見てもらって落としどころを探れれば尚ヨシです。
このサドルポイントを探る考え方は、実はとても汎用的です。例えば、市場の需要と供給のバランスを探る場合を例にとって考えてみると、ある商品の売れ行きが良いので、供給量を少し増やしてみたら、まだ売れた、もう少し増やしてもまだ売れた、もう少し増やしたら在庫が出た。極端に単純化した話ですが、在庫が出るちょっと前がバランスするポイントになるといったイメージです。デザインの調整でも無意識のうちにやっていることだったりしますが、最適化するのに、どこまで小さく(或いは大きく)すれば良いかという問題や色の濃さなどに関する問題は、最適解を求めるという問題ほかならないので、考え方として応用が可能になります。
また、この最適解が、なぜサドルポイントと呼ばれるかについてですが、英語表記では、「saddle」で日本語訳すると「鞍」とか或いはそのまま「サドル」です。鞍は馬の背のような形になっていて高さとしての頂点をもちますが、それに似て二次曲線の極値のような形になる性質があるのでサドルポイントと名づけられているそうです。
実作業としては、調整作業の繰り返しになるので、成果物となるUIの完成形のみからは思いもよらないほどの作業工数を消費してしまったりすることもあるのですが、excellentなデザインを作り出す必要があるといったケースでは、この地道で骨の折れる作業をひと踏ん張りしてやってみてもよいのではないでしょうか?
以上ご参考まで。