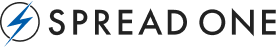デザイナーの承認欲求
成果物と承認欲求
デザインの仕事をしていると自分の成果物に対するフィードバックを会社の内外から受けることになりますが、今回はフィードバックを受ける際の心構えについてです。これだけだと精神論っぽいですが、脳の働きについて(書いたつもり)です。
デザイナーにとって作成した成果物を褒められれば普通は嬉しいですし、逆に大小さまざまなダメ出しがきて気分のよい人はあまりいないでしょう。つまり、程度の差こそあれ自分の成果物に対する承認欲求が働いているわけですが、この承認欲求の強さは、デザインの仕事をする上で、冷静さを欠いてしまいロクなことにならない要因にもなるのだそうです。 今回の記事では、そのメカニズムを考え、対処法も調べたので自戒の念も込めてブログに書き残しておきたいと思います。
欲求と脳の働き
まず、仮定として承認欲求を強くもっているとします。すると、フィードバックする相手に自分の承認欲求を満たしてほしい、簡単に言うと褒めてほしいと無意識のうちに身構えてしまいます。その結果、欲求が満たされずにネガティブなフィードバックが返ってきてしまった場合、何が起こるかと言うと、感情をコントロールする脳の部位が刺激され、感情が乱れてしまいます。頭に血が上るとよく言いますが、物理的に紛れもない事実だそうで、感情が乱れると脳に過剰に血液が供給され、脳が酸欠状態に陥ってしまうのだそうです。たくさんの血液が供給されて酸欠になるというのは、矛盾しているようにも感じますが、脳が過呼吸のような状態に陥るのかなと自分では解釈しています。
ここで厄介な事実として、感情をコントロールする脳の部位のすぐ隣に思考をコントロールする脳の部位が物理的に存在している点です。感情が乱れて脳が酸欠状態になってしまうと隣にある思考をコントロールする脳の部位も著しく機能が低下してしまうのだそうです。デザイン業務に目を向けると、フィードバック後に再提出されたものを再度レビューした際、明確に指示したはずなのに、いくつも修正漏れがあったり、逆に頼んでもいないことをやっていたりといった事象が起こる原因(のウチの少なくともひとつ)は、感情の乱れによる思考力の低下なのではないかと考えています。つまり、指示を頑張って聞いてはいますが、思考力が著しく低下し正常に機能していないため、正確に情報をキャッチできなくなっているといった状態です。
自己肯定感との関係
では、この厄介な承認欲求は、どこから来るのかと言うと、実は、自己肯定感と密接に関係しているのだそうです。もし、自己肯定感が高ければ、他人からの評価でいちいち動揺せず、落ち着きを保てるため、素直にネガティブなフィードバックであっても受け入れることができます。そしてフィードバック後も、速やかにやるべきタスクをこなすことができます。逆に、自己肯定感が低く自分に自信がない場合、他人からネガティブなフィードバックによって感情が乱れてしまいます。 更には、動揺して感情が乱れてしまうと前述の通り脳が酸欠になり、思考力が低下するため、フィードバックの内容をしっかり理解し記憶できず、速やかにやらなければならないタスクも上手くこなせなくなってしまうというメカニズムです。自己肯定感や感情の抑制というのは一朝一夕でできる簡単なことではないので、結構やっかいな問題かと思います。
嫉妬や認知の歪みの問題
もうひとつ過度な承認欲求によって生じる問題があります。嫉妬です。デザイン能力の高い同僚が褒められたのに自分が褒めてもらえないという状況に陥った際、ストレートに事実を認識して、謙虚にあの人のデザイン能力は凄い!自分もあんな風になれるように頑張ろう!それには、自分の成果物とどこが違うのか冷静に分析してみよう!となれば良いのですが、自己肯定感が低く、嫉妬の感情に飲み込まれてしまっては、そうはいかないということは想像に難くありません。嫉妬の感情によって、あの人ばかり褒められているのは、贔屓されているのではないかとか、余計な事ばかり考えてしまい感情が安定しなくなってしまいます。そんな子供っぽい感情を持つか?と思われるかもしれませんが、現実的には嫉妬の感情を抑制するのも非常に難しいことかと思います。デザインの仕事に限らずですが、同僚が褒められているのに自分は全く褒められないという状況に直面したら、この記事を書いている私自身も間違いなく凹むはずです。また、厄介な事としては、事実として、ユーザから「使いにくい」とか「判らなかった」と伝えられても事実を歪曲してしまい認めようとしないという現象が起こります。つまり認知の歪みまで生んでしまことも起こります。「使いにくい」「わからない」とコメントしたユーザは、本当にターゲットユーザなのか?偶然1人が言っただけじゃないか?(他のユーザは違うはず・・・)といった調子です。言うまでもなく、事実を事実として真摯に受けとめるのを拒むようなスタンスは、とても感心できるものではありませんが、認知の歪みは、自分では自覚できないことのほうが一般的なのでこれも簡単な問題ではないように思えます。
メンタルの乱れの対処方法のあれこれ
さて、この承認欲求の強さによる負のスパイラルですが、対処方法としては、デザイナーであれば、自分の成果物に心血を注ぎ過ぎる前のまだ軽い段階でフィードバックを受けるのがよいと考えています。「デザインは質か量か」で書いたことですが、デザインのプロセスで早く、安く、たくさんのにラフ案を出し素早くフィードバックを受けるのは、優れたアイデアを練り上げるためのプロセスです。しかし、その一方で、見方を変えるとデザイナーの承認欲求の肥大化を防ぎ、冷静さを保ってスピーディにタスクをこなしていくためにも必要なプロセスだと言えるのではないかと思います。経験上、精魂をかけて費やした時間と承認欲求の肥大化には関係があります。また、そんなにたくさんのアイデアを出す時間がない場合でも、承認欲求を強く持ち過ぎるとロクなことがないというのは、自戒の念も込めてですが、肝に命じておいたほうがよいのではないかと思います。
また、「感情を安定させる」というところにフォーカスを当てると、別のアプローチもあるようです。昨今では、ビジネスマンの浸透しつつありますが、まず効果的なのは運動です。運動はあらゆる脳の部位に良い影響があることは、科学的にも証明されているので、定期的な運動は、デザイナーであってもなくても心がけるとよいようです。他にも感情コンロトールする力を鍛える方法として、意識的に嗜好品を我慢するのが良いトレーニングなるそうです。例えば、コーヒーやたばこを我慢するとか、スマホを頻繁に見てしまう場合には、少しの時間、スマホを絶つことで、感情を制御する脳の部位を鍛えることができるのだそうです。
一般的に感情系の脳部位は、成長がとても遅く、一生をかけてゆっくりと成長していくという特徴をもつ部位なのだそうです。(心穏やかになった老人の姿を想像するとその話も納得がいきます。)また、感情をコントロールする部位を自分で鍛えられるという事実は、感情の制御が苦手で瞬間湯沸かし器的な性格はどうにもならないと諦めていた人(自分 笑)からしてみると、救いの手を差し伸べられているような話である気がしています。ちなみに、意識的に我慢する時間を作っていくと、2~3週間で脳に物理的な変化が起こり、次第に感情を制御する力も鍛えられていくそうです。私も感情が乱さず思考能力がクリアな状態を保つのに苦労している面は多々あるので、継続的に嗜好品を我慢するチャレンジをしてみたいと思います。(手始めはコーヒーあたりから・・←独り言)
以上ご参考まで。